福岡市での夏の室温を賢く下げる「遮熱屋根塗装」施工事例(スレート屋根・屋根塗装工事)

物件データ
- 施工エリア
- 熊本県八代市
- 工事内容
- 屋根塗装工事
- 屋根材
- スレート屋根
- 屋根プラン
- 使用塗料:遮熱塗料
- 工事期間
- 約3週間
- 工事完了月
- 2025年9月
お客様の声
午後になると2階がむっとするのが当たり前でしたが、工事後はエアコンの効きが早くなり、設定温度を上げても快適に感じます。工事中の近隣配慮や進捗の報告が丁寧で、不安なく任せられました。台風前に板金も直してもらい、安心して秋を迎えられます。

施工レポート
施工前
施工前
全体として塗膜の樹脂分が抜け、艶が引けたことで素地の微細な凹凸が強調され、特に南面は粉をまとうようなチョーキングが手に触れるだけで付着する状態でした。重なり部には長年の微細な堆積物と藻の根が入り込み、毛細管現象で雨水が滞留しやすくなっており、乾燥後も縁が貼り付いたままの箇所が散見されました。スレート端部はエッジが丸く摩耗して吸い込みが不均一、局所的に素地が露出し、雨だれ筋に沿って色ムラが帯状に残っています。棟板金は固定釘の頭に軽い赤錆と浮きが見られ、風を受けた際のバタつき音が想像できるレベルで、継ぎ目のシーリングは痩せてひび割れ、雨の吸い上げリスクが高い状態でした。踏査時の体感としては直射下で屋根面の熱だまりが強く、手をかざすと放射熱の反射が少ないため、熱が面内にとどまりやすいことが読み取れ、小屋裏のこもり熱が生活環境に影響している兆候が出ていました。雨仕舞いの観点では、ケラバ・軒先の通りが乱れていて水切れの“走り”が鈍く、降雨後の乾きにムラが出る典型的な劣化ステージに入っていました。
施工後
施工後
下地の傷みを拾わないよう吸い込みを整えたうえで、均一な膜厚で仕上げたため、屋根面は面精度が整い、稜線からケラバに伸びる直線の通りが美しく復元されています。高日射反射性のある仕上げにより、直射下でも手を近づけた際の熱気の立ち上がりが穏やかで、表面が熱を抱え込まずに光を返す「軽い」印象に変わりました。縁切りを確保した重なり部は雨筋の走りが滑らかで、水が迷わず排出されるため、溜まりによる汚れ戻りが起きにくい状態です。棟板金は再固定と継ぎ目のシーリング打ち替えで雨仕舞いがタイトになり、風を受けても余計な共振が出ない安定感があり、台風期の耐風性にも好影響が期待できます。全体の発色は均一で、斜光時に現れる艶の“面”が途切れずに連続しており、遠景でもスレートの段差陰影が整って見えるため、意匠性と機能性の双方が底上げされています。仕上げ後の散水確認では、谷部・軒先・ケラバの排水ラインに滞りがなく、雨水は面から線へ、線から点へとスムーズに流下。乾き上がりも均一で、今後の汚れ定着や苔の繁殖抑制に寄与する健全な状態に仕立て直せています。
工場のスレート屋根の屋根塗装工事のコツ
工場のスレート屋根を長持ちさせる塗装は、工程の順番と“見えない管理”がすべてです。まずは操業との調整から始め、搬入口や給排気口、屋上機器(換気扇・集塵機・クーリングタワー)の稼働時間を把握し、粉塵やミストが製造ラインに入らない風向・時間帯を選びます。墜落災害防止のために親綱・ライフライン・開口部の養生を先行し、折板ではないスレート特有の踏み抜きリスクに備えて歩廊板を敷設します。既存材は築年によりアスベスト含有の可能性があるため、事前調査と適切な除去・封じ込め手順を確定してから高圧洗浄に移行します。洗浄は苔・藻・粉化塗膜をルーフドレン方向に流し、雨樋や竪樋に堆積させないよう集排水マットで捕集し、乾燥は含水率で管理して早塗りを避けます。下地調整では、微細クラックは弾性パテで面ではなく線で追い、釘・ビス浮きは座金交換や増し締めで面の揺れを止め、棟包み・ケラバ・谷樋・明かり取り周りのシーリングは脆化部を撤去してプライマーからやり直します。スレートの重なりは毛細管現象で水を抱え込みやすいので、縁切りのためにタスペーサーを計画的に挿入し、閉塞を残さないことが雨仕舞いと通気の肝になります。下塗りは含浸型プライマーで吸い込みを均一化し、脆弱層を固めたうえで、必要なら下塗りを増し入れして上塗りにチョーキングを拾わせません。中・上塗りは仕様ごとの規定膜厚(DFT)を必ず確保し、ローラーなら目潰し→ならしの順で段差を消し、吹付なら風速・ノズル径・吐出量を記録してオーバーミストを防ぎます。夏季の工場屋根では高日射反射(遮熱)塗料が効果的ですが、下地の平滑度と膜厚管理が反射効率に直結するため、ウェット膜厚ゲージで各面のWFTを測定し、乾燥硬化の再塗装間隔(可使時間)や露点差・相対湿度も場内のデータとして記録します。付帯部は先行して錆を除去し、ボルト頭や金物はジンクリッチで下塗りを分けて電食を抑え、異種金属の接触部には絶縁を挟みます。換気フードやソーラーパネル、ケーブルラックの取り合いは毛細上がりを起こしやすいので立上りの塗り代とシールの三面接着を避ける納まりを徹底し、特に谷部は水線が直線で走るか散水で必ず確認します。品質確認は目視だけでなく、クロスカットや付着力簡易試験、赤外線サーモでの熱だまり低減の実測、散水による排水の“走り”確認まで行い、是正が出た場合は面ではなく原因点に遡って補正します。環境配慮としては洗浄汚水や剥離粉の流出防止、溶剤臭の時間帯管理、近隣車両へのミスト対策、フォークリフト動線との交錯回避計画を事前に図面化し、日々のKYと合わせて共有します。引渡し時には、清掃頻度(年1〜2回の低圧洗浄)、排水経路の点検、板金・シーリングの経年点検サイクル、再塗装目安、禁忌事項(強い高圧直噴・重歩行・縁切り部の目詰まり)を明文化し、操業カレンダーと連動したメンテ計画をセットで渡すことで、塗って終わりではない“運用で劣化を遅らせる”体制まで整えるのがプロのコツです。


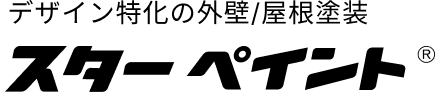

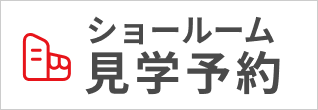




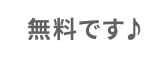











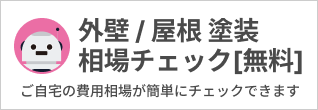



担当者より
スレート特有の微細なクラックや重なり部の閉塞は、遮熱効果以前に雨仕舞いの信頼性を損ないます。今回は洗浄→補修→縁切り→3工程塗装の「順番」と「乾燥時間の厳守」にこだわりました。特に下塗りの吸い込みムラは上塗りの色艶と耐候性に直結するため、下地の状態を見ながら塗布量を微調整しています。仕上がり後は屋根面の熱だまりが和らぎ、日中の小屋裏の熱気も軽減。台風シーズン前に板金部の固着とシーリングを入れ直せたのも、長期的な安心につながるポイントです。